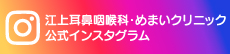『亜鉛不足で味覚障害になる原因について』
2023年9月22日
食べ物の味を感じにくくなる、あるいは感じられなくなる味覚障害にはいくつかの原因があります。
中でも特に多い原因が亜鉛不足です。
亜鉛が不足すると味覚に問題が生じるのはなぜでしょうか?
また、亜鉛不足を補うには何を食べればいいのでしょうか?
亜鉛不足について、解説します。
亜鉛不足でなぜ味覚障害が起こるのか?
亜鉛と聞くと、金属を思い浮かべる人もいるかもしれません。
亜鉛は鉄分と同じく、人間の体には必要不可欠な栄養素であり、体内では筋肉と骨中、皮膚、肝臓など様々なところに存在しています。
亜鉛は体内には約2g存在しているといわれています。亜鉛が不足した場合、味覚障害になってしまうのです。
なぜ、亜鉛不足で味覚障害になるのでしょうか?
亜鉛不足が味覚障害の原因となるのは、味蕾に原因があります。
味蕾は舌にあって中に味細胞が含まれていて、味を感じる働きがあります。味細胞は体の中でも特に新陳代謝が活発な細胞です。
約30日おきに置き換わる味細胞の新陳代謝には、亜鉛が必要です。亜鉛が不足していると、新陳代謝ができなくなってしまいます。ただし、亜鉛は約30%しか吸収できない点に注意が必要です。よって、亜鉛を摂取する際は、成分表を見ながら必要量の約3倍の量を摂取しなくてはいけません。
亜鉛が豊富な食材は?
亜鉛が不足したときは、サプリメントや内服薬で補えばいいと思う人もいるでしょう。
サプリメントや内服薬で補うことは可能ですが、できれば食生活を改善した方が、健康的な生活を送ることができます。
亜鉛は具体的にどのような食べ物に含まれているのでしょうか?
亜鉛を多く含む食材で代表的なのが、牡蠣のような魚介類です。
他にも、多くの貝類に含まれています。また、煮干しも亜鉛が豊富です。
亜鉛はほかに牛肉にも含まれています。ゴマ、カシューナッツなどのナッツ類や、黄な粉などの豆類、薄力粉のような穀類、抹茶、ココアなどの飲み物にも亜鉛は含まれているので、意識していれば摂取しやすいでしょう。
まとめ
味覚障害の原因として多いのが、亜鉛不足です。
亜鉛は貝類や牛肉、豆類、穀類、ココアなどの飲み物、ナッツ類など様々なものに含まれている成分ですが、食生活の偏りによって不足しがちです。
亜鉛が不足すると、味を感じる味蕾の中の味細胞の新陳代謝ができなくなるので、きちんと摂取しておく必要があります。
どうしても難しいな場合は、サプリメントなどを服用してください。
当院では血液検査で亜鉛をチェックして、低下があれば亜鉛を内服で補充しつつ、亜鉛が多く含まれる食事指導を行なっています。味覚障害でお悩みの方は、是非、ご相談下さい。
Instagaramも更新しておりますので、登録よろしくお願いします。